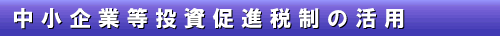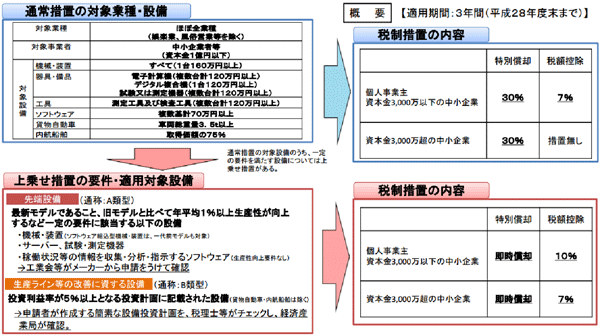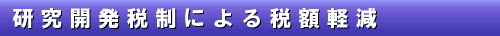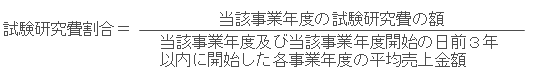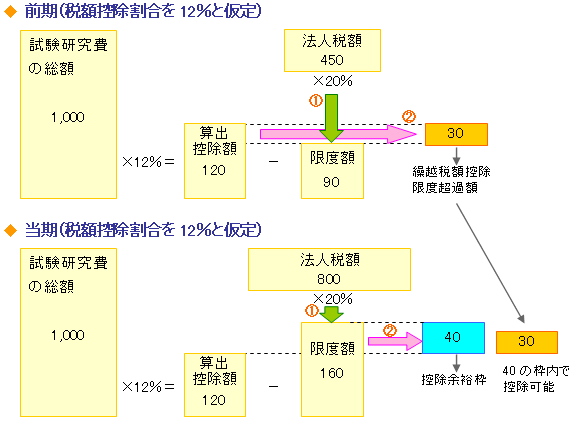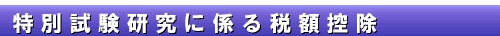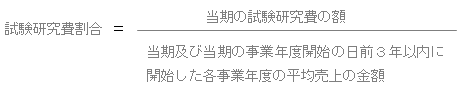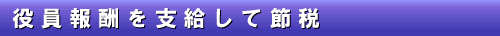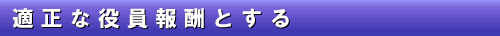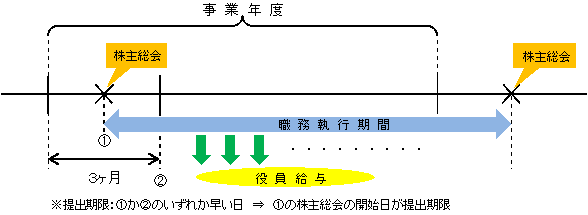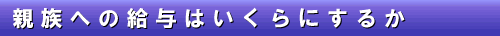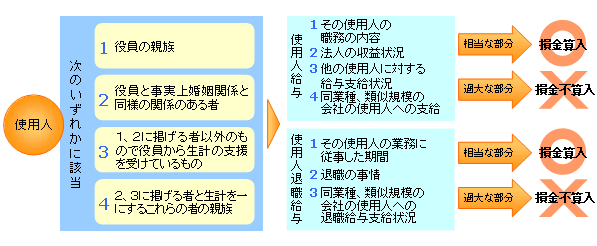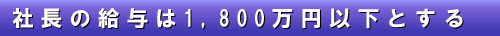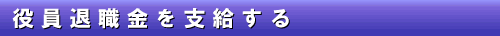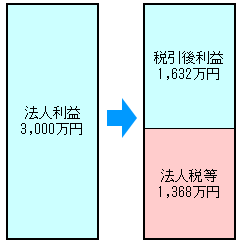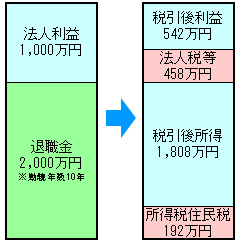「特別試験研究に係る税額控除制度」とは、その事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額のうちに特別試験研究費の額がある場合において、その特別試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。
| ① | 中小企業技術基盤税制との重複適用はできません。 | | ② | 控除の明細を添付することになります。 |
|
(1)適用対象年度
この制度による税額控除の適用を受ける場合において、特別研究税額控除限度額が法人税額の20%相当額(※注1)を超えるため特別研究税額控除限度額の全部を控除しきれなかったときには、その控除しきれなかった金額については、一定の要件の下に1年間の繰越しが認められます(※注2)。※注1 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度においては、30%相当額となります。
※注2 平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度における繰越税額控除については、特例が設けられています。
(2)特別試験研究費の額等
この制度の対象となる特別試験研究費の額とは、試験研究費の額のうち、国の試験研究機関又は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究などに係る試験研究費の額をいいます。
また、試験研究費の額とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する原材料費、人件費及び経費のほか、他の者に試験研究を委託するために支払う費用などの額をいいます。ただし、試験研究に充てるために他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額が試験研究費の額となります。
(3)特別研究税額控除限度額
この制度による特別研究税額控除限度額は、その事業年度の損金の額に算入される特別試験研究費の額に特別研究税額控除割合(12%-試験研究費の総額に係る税額控除割合)を乗じて計算した金額です。
| ①比較試験研究費の額 | 比較試験研究費の額とは、適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額を平均した額をいいます。 | | ②基準試験研究費の額 | 基準試験研究費の額とは、適用年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額のうち最も多い額をいいます。 |
(A)試験研究費の総額に係る税額控除制度| ● | 控除限度額 | | | | 試験研究費の額 × 税額控除割合(※)
(※)税額控除割合
●試験研究費割合(注1)が10%以上の場合・・・10%
●試験研究費割合が10%未満の場合・・・
(試験研究費割合×0.2)+8%
(注1)試験研究費割合とは次の算式により計算した割合した割合をいいます。
[算式]
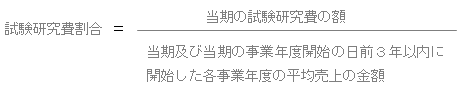 | | | (注2)控除できる金額は、その事業年度の法人税額の20% (平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度においては30%)相当額が限度となります。 | | | |
(B)特別試験研究費の税額控除| ● | 控除限度額 | | | 特別試験研究費の額×(12%-上記(A)の税額控除割合) | | | (注)
控除できる金額は、当期の法人税額の20% (平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度においては30%)相当額からAで適用された税額控除額を控除した残額が限度となります。 |
(C)中小企業技術基盤強化税制| ● | 控除限度額 | | | 次のいずれか少ない金額となります。 | | | ①当期の試験研究費の額 × 12%
②当期法人税額×20%
(平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度:当期法人税額×30%) |
(D)試験研究費の増加額等に係る税額控除制度
(上記A~Cの制度とは別枠で適用できます。) | ● | 控除限度額 | | | 次の①②のいずれかの金額(選択適用)と、③のいずれか少ない金額となります。 | | | ①(試験研究費の額-比較試験研究費の額)×5%
②(試験研究費の額-平均売上金額×10%)×超過税額控除割合(※)
(※)超過税額控除割合=(試験研究費割合-10%)×0.2
③当期法人税額×10% |
|
税額控除限度額のうち法人税額から控除しきれなかった金額は、1年間に限って、繰り越されます。
青色申告法人が対象です。
損金の額に算入される試験研究費だけが対象です。繰延資産は対象外となります。中小企業の経営において事業承継は大きな問題です。さらに親族が、後継者になるためには、会社の業務及び経営状況を理解するだけでなく、得意先の信頼を得るためにも、経営者とともに仕事をすることは大変役立ちます。法人の場合は仕事に従事していれば給与を支給することができます。また、親族が役員となれば、役員として給与を支給することができます。
役員報酬を利用した節税には、以下の2つがあります。
| ① | 役員報酬の増額等 | ・・・ 利益の圧縮、所得の分散による節税 | | ② | 法人成 | ・・・ 給与所得控除を活用した節税 |
|
| ① | 定時同額支給しなければならない。 | | ② | 議事録など完備しなければならない。 | | ③ | 毎期一定時期にしか給与の増額ができない。 | | ④ | 不相当に高額な金額は損金にならない。 |
|
法人成りすると、経営者は会社から給料(役員報酬)を支給されることになります。
ここで重要なのは、給与所得には給与所得控除というものがあり、給与の額に応じて一定の控除をうけることが、法人の利益を圧縮するだけでなく、役員の所得も圧縮できます。
金額については、以下の表を参照してください。
| 給与額 | 給与所得控除額 | | 超 | 以下 | | 0 | 650,000 | 給与額×100% | | 650,000 | 1,625,000 | 650,000 | | 1,625,000 | 1,800,000 | 給与額×40% | | 1,800,000 | 3,600,000 | 給与額×30%+180,000 | | 3,600,000 | 6,600,000 | 給与額×20%+540,000 | | 6,600,000 | 10,000,000 | 給与額×10%+1,200,000 | | 10,000,000 | | 給与額×5%+1,700,000 |
企業の業績が良くなり役員報酬を増額していくことにも限界があります。現在の法人税の税率は最高で30%ですが所得税は、40%となっております。そこでも配偶者や親族が、役員になっている場合、代表者が行っている業務を委譲して役員報酬額を分散することも節税へとつながります。そこで下記のシュミレーションをしてみました。
【前提条件】| ① | 扶養親族は、奥様以外はいない。 | | ② | 奥様も役員である。 |
|
| 社長 | 奥様 | 合計 | | 給与額 | 24,000 | 960 | 24,960 | | 税額 | 5,640 | 0 | 5,640 |
 | | ●改定後 | | (単位:千円) |
| 社長 | 奥様 | 合計 | | 給与額 | 18,000 | 6,960 | 24,960 | | 税額 | 3,214 | 509 | 3,723 |
上記のように役員報酬を分散することにより所得税額が大きく減少します。
奥様に社会保険料が発生したとしても節税メリットがあり、世帯の可処分所得も増加するといえます。
法人成による節税として給与所得控除による節税があります。(例) 個人 事業所得500万円で所得控除が200万円の場合の税額
500万円(事業所得)-200万円(所得控除)=300万円(課税所得)
300万円(課税所得)×20%-9万円=51万円(所得・住民税額) |
(例) 法人 法人所得500万円で役員報酬が500万円の場合の税額
500万円(法人所得)-500万円(役員報酬)=0万円(法人課税所得)
●役員給与分所得税
500万円(役員報酬額)-154万円(給与所得控除)=346万円(給与所得)
346万円-200万円(所得控除)=146万円(課税所得)
146万円×15%=21.9万(所得・住民税額)
21.9万円(所得・住民税額)+7万円(法人税額)(注1)=28.9万円 |
(1)役員報酬の会社法の制約
役員が自らの報酬を自由に決定できると、いわゆる「お手盛り」になるおそれがあるため、会社法は、役員報酬について、定款でその額を決めておくか、株主総会の決議で定めることと制約を課しています。(会社法361条参照)
(2)税法上の制約
法人税においては、役員報酬は、その役員に対する業務遂行の対価であるため、原則として、損金の額に算入できます。これに対し、役員賞与は、業務遂行の対価ではなく、利益処分の性格を有するため、損金の額には算入されません。報酬が損金になり賞与が損金にならないとなると、本来、役員賞与として支給するべきものを役員報酬の名目で支給して税金の負担を軽減しようとすることが考えられることから、役員報酬の額のうち役員の職務に対する対価として相当な額を限度として損金の額に算入することができるとされています。
つまり、会社が支給する役員報酬が不相当に高額である場合には、その高額と認められる部分の金額は、損金の額に算入できないということです。高額かどうかは、次の「実質基準」及び「形式基準」で判定します。
| ① | 実質基準… | その役員の職務の内容、会社の収益、使用人に対する給料の支給状況、同業種同規模会社の役員報酬の支給状況等からみて適正かどうか判定する基準 | | | | ② | 形式基準… | 定款の規定又は株主総会等の決議により定められた報酬の額を超えていないかどうかで判定する基準 |
|
定期同額給与とは、1ヶ月以下の期間を単位(毎月・毎週など)とし、定期的に同一の金額を支給する役員給与をいい、以下の要件のいずれかに該当するもののことをいいます。| ① | 定期給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの | | | | ② | 定期給与について、給与改定がされた場合には、その事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの | | | | ③ | 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
※ 毎月供与される一定額の経済利益の具体例
→社宅などの家賃、金銭貸付利息、保険料等 |
|
また、②の給与改定では以下の要件に該当していなければなりません。| ① | その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までにされた定期給与の額の改定。ただし、継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その3か月を経過する日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの | | | | ② | その事業年度において臨時改定事由によりされた役員に係る定期給与の額の改定(①に掲げる改定を除きます。) | | | | ③ | その事業年度において業績悪化改定事由によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、①及び②に掲げる改定を除きます。) |
|
その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めについて支給する給与で、その給与に係る職務の執行を開始する日(定時株主総会等の開催日)と会計期間3月経過日とのいずれか早い日までに、納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている給与をいいます。
【事前確定給与のイメージ】
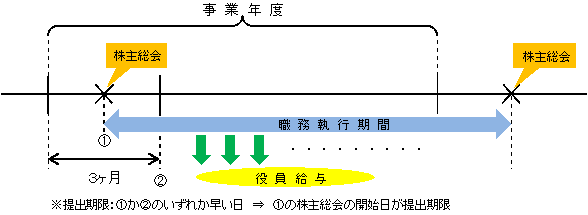
また、既に届出をしている法人が、その届出に係る定めの内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に基因するものであるときは、その変更後の定めの内容に関する届出はその事由の区分に応じて次に掲げる日までに行わなければなりません。| ① | 臨時改定事由 | | → | その事由が生じた日から1か月を経過する日 | | | | ② | 業績悪化改定事由 | | → | その事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日が1か月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日) |
|
利益連動給与とは、非同族会社が業務を執行する役員に対して支給する役員給与で次の要件をいずれも満たし原則として損金算入できる役員給与をいいます。
なお、特定の業務執行役員のみの支給は適用の対象外になります。
【適用要件】| ① | その算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。 | | | | イ) | 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。 | | | | | ロ) | その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに一定の報酬委員会が決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続きを経ていること。 | | | | | ハ) | その内容が上記ロの決定又は手続き終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。 | | | | | ② | 有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標の数値が確定した後1か月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。 | | | | ③ | 損金経理をしていること。 |
|
給与を決定する場合には、法人税法で定められた範囲で支給することが重要です。支給する親族が役員である場合と従業員である場合に分けて説明いたします。
(1)適正な役員報酬とは
親族が役員の場合、他の役員と同じ基準で以下のポイントに気をつけて支給額を決定します。
役員報酬を活用した節税には、以下の2つがありまた特徴があります。
| ① | 職務内容、責任レベルに見合った報酬であること | | ② | 同業者・同規模の企業と比べて過大でないこと | | ③ | 常勤、非常勤など勤務実態に見合った報酬であること |
|
(2)株主総会・取締役会で承認を得る
同族の者が資本の大部分を持ち、経営支配権を握っているような同族会社については、法人税などの税負担を不当に減少させることを目的に、非同族会社では容易にできないような取引や計算を行った場合、税務署長はそれを否認することができるとされています。
取締役の報酬については、定款に当該事項を定めていないときは株主総会の決議によることとされていますが、一般的には、その総額は株主総会で決議し、各取締役の報酬額については、取締役会の承認を得ることになっています。なお、総会・取締役会等の開催後には必ず議事録を作成し、きちんと保存しましょう。社長の親族である奥様や息子に給与を支給することにより、社長1人で給与を受け取る場合よりも税額が低く抑えられます。これは、所得税は『超過累進課税』であり、所得が多くなるに従い高い税率を適用されることとされているためです。
これを回避すべく所得の分散を行うことにより、分散する社長からは高い税率が適用される所得から削られていき、分散された親族側の所得には低い税率から適用されますので、世帯全体の収益性を下げずに税負担だけ抑えることができます。
【条 件】| ① | 社長の給与は12,000千円(A案) | | ② | 世帯で給与の合計が12,000千円となるように奥様に支給(B、C案) | | ③ | 扶養は2人で、扶養控除と基礎控除以外の所得控除は考慮しない。 | | ④ | 業務内容等は一切考慮しない。 |
|
| A案 | B案 | C案 | | 社長 | 奥様 | 社長 | 奥様 | 社長 | 奥様 | | 給与 | 12,000,000 | 0 | 8,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | | 世帯給与計 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | | 所得税 | 1,153,400 | 0 | 544,500 | 130,500 | 214,500 | 140,000 | | 住民税 | 798,000 | 0 | 501,000 | 233,000 | 327,000 | 393,000 | | 合計 | 1,951,400 | 0 | 1,045,500 | 363,500 | 541,500 | 533,000 | | 世帯税額計 | 1,951,400 | 1,409,000 | 1,074,500 | | 節税額 | ― | 542,400 | 876,900 |
上記のように、A案のように社長1人で12,000千円の給与を受けとった場合には税額計が1,951,400円だったのに対し、B案のように社長8,000千円・奥様4,000千円の支給とするだけで542,400円の節税になり、C案のように社長6,000千円・奥様6,000千円の支給とした場合には876,900円の節税になります。
ただし、税務調査では仕事の従事量や責任の重さなどを問題にされます。C案のように社長と奥様が同額では、従事量が同じだったとしても責任レベルが全く違うため、奥様の給与の過大部分が否認されてしまいます。結果としてこの場合はB案にすることが妥当と思われます。
給与を決定する際は税理士等によく相談し、決定することをお勧めします。役員に対する給与は、報酬、退職給与、賞与の3種類があります。賞与を除いて、役員報酬と役員退職給与については適切な額であれば全額損金に算入されますが、不相当に高額な部分の金額については損金に算入されません。
一方、使用人給与(退職給与を含む)については、税法上このような制約が存在しないことから、役員の親族を故意に役員にしないで、使用人として多額の給与を支給するなど、いわゆる租税回避する例が多く見受けられることなどから、平成10年4月1日以後開始する事業年度より役員の親族である使用人に対する過大な給与については損金の額に算入しないことになりました。
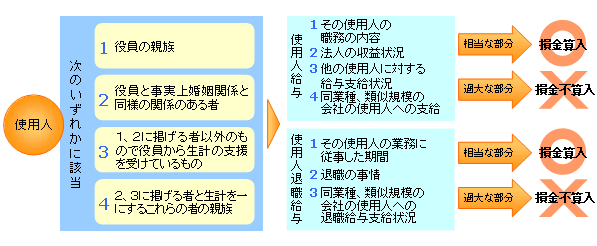 役員報酬を支給する場合は、その報酬額が適正であるかどうかが重要となります。税務調査で役員報酬が過大であるとされた場合、否認された部分に対して法人税が課税となって、余計な税金を払うことになってしまいます。 役員報酬を支給する場合は、その報酬額が適正であるかどうかが重要となります。税務調査で役員報酬が過大であるとされた場合、否認された部分に対して法人税が課税となって、余計な税金を払うことになってしまいます。
また、通常の支給では損金不算入である役員賞与も、事前に届出を提出することにより損金として認められます。役員報酬を支給する場合は、税法上の規定をよく理解し、適正な報酬額となるようにしましょう。
法人にかかる法人税の税率と社長(個人)にかかる所得税を比較してみると、次のようになります。個人は、所得が増えれば増えるほど、税率が高くなっていくという超過累進税率になっています。これに対し、法人は一定税率となります。
【個人事業の課税所得に対する税率】| 所得金額 | 所得税率 | | 195万円以下の部分 | 5% | | 195万円超~330万円以下の部分 | 10% | | 330万円超~695万円以下の部分 | 20% | | 695万円超~900万円以下の部分 | 23% | | 900万円超~1,800万円以下の部分 | 33% | | 1,800万円超の部分 | 40% |
【法人事業の課税所得に対する税率】(※資本金1億円以下の場合)| 所得金額 | 法人税率 | | 800万円以下の部分 | 22% | | 800万円超の部分 | 30% |
役員報酬による節税効果を考える場合、法人税だけでなく、所得税にも注意する必要があります。
所得税の場合は最低税率5%から最高40%までありますが、法人税の場合は資本金1億円以下の場合であれば最低税率22%から最高税率でも30%までしかありません。役員報酬を支給することにより法人税を節税できたとしても、その節税額以上に社長個人の税額が増えてしまっては意味がありません。
そこで、税負担から節税の分岐点を探り、その分岐点を目安にして給与金額を決定することになります。
【 条 件 】| ① | いずれも法人の所得と社長の給与の合計額が3,000万円になるように設定 | | ② | 法人は資本金300万円 | | ③ | 社長の扶養は2名で、扶養控除以外は考慮しない |
|
【 シミュレーション結果 】 | A案 | B案 | C案 | | 法人 | 社長 | 法人 | 社長 | 法人 | 社長 | | 利益/給与 | 18,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 18,000,000 | 6,000,000 | 24,000,000 | | 利益・給与合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | 法人税/所得税 | 4,760,000 | 1,332,800 | 2,960,000 | 3,169,800 | 1,320,000 | 5,188,000 | | 住民税 | 2,459,700 | 875,500 | 1,529,100 | 1,445,500 | 676,000 | 2,015,500 | | 合計 | 7,219,700 | 2,208,300 | 4,489,100 | 4,615,300 | 1,996,000 | 7,203,500 | | 税額合計 | 9,428,000 | 9,104,400 | 9,199,500 | | 節税額 | | A案より 323,600 | A案より 228,500 |
上記のように、B案が一番法人と社長個人の納税額の合計が低く抑えられています。C案のように役員報酬を取りすぎてしまうと、法人の節税額以上に社長個人の納税額が増えてしまいます。
社長の所得控除等の条件により結果は様々ですが、このように法人と社長のバランスを考え、状況ごとにシミュレーションを行い、最適な役員報酬を決定することが重要です。役員退職金は、その金額が過大でない限り損金の額に算入することが認められています。したがって、役員退職金を支給することで、法人税の節税にもなります。
退職金支給は法人にとって、大変メリットの多い節税方法と言えるでしょう。
(1)退職金支給時比較表 退職金は永年の勤労に対し支給されますので、「退職所得」として他の所得と分離して課税されます。
(1)退職所得に該当するもの
勤務先から受ける退職金や一時恩給 (小規模企業共済からの一時金なども含む)
(2)退職金課税対象額の計算| 退職金課税対象額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
【退職所得控除額の速算表】(勤続年数の端数は切り上げ)| 勤続年数 | 退職所得控除額 | | 20年以下 | 勤続年数×40万円 (最低保証80万円) | | 20年超 | (勤続年数-20年)×70万円 -800万円 |
退職所得は、「分離課税」であり、通常は支払いを受ける際に、源泉徴収されて課税関係は終了。
(3)所得税・住民税の算出
(2)で算出した課税対象額をもとに、所得税額、住民税額を計算します。
実務上は役員退職金の計算方法は、次の2つが使用されております。
(1)退職金計算方法 【功績倍率方式】| 適正な退職金 = 最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率 |
【参考功績倍率】| 会長・社長 | 2.3~2.5倍 | | 専務 | 1.9~2.1倍 | 常務 | 1.8~2.0倍 | | 取締役 | 1.5~1.8倍 | | 監査役(常勤) | 1.5~1.8倍 |
| ※平成17年度「役員報酬・賞与・退職慰労金」産労総合研究所 |
【1年当たり退職金平均金額法】| 退職金相当額=比較法人の1年当たり退職金平均金額 × 勤続年数 |
|
 | ① | 役員退職金の支出が、定款、株主総会及び取締役会の決議に基づいていること。 | | | | ② | 具体的に支給することが確定した日、又は実際に支給した日を含む事業年度において損金経理していること。 | | | | ③ | 退職金の額が、その役員の在任期間、退職に至った事情、同規模他社における役員退職金の支給状況などに照らして不相当に高い金額でないこと。 | | | | ④ | 退任後は、完全に第一線から退くか、オーナー社長などの場合は代表権のない会長等に就任するようにし、その場合の役員報酬の額は、退任直前の報酬金額の半分以下とすること。
|
|
|
|
|
|
|