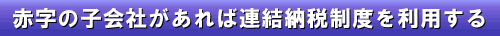熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。
税理士法人新日本(熊本市)
明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応,不動産
税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方
無料相談実施中
土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください
860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00
096-288-4080
法人税の節税 子会社や別会社を使った節税
   | 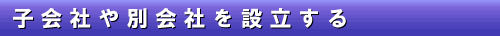 |
| 1 税率の差で節税する |
事業が順調になってくると利益も相当なものとなってきます。このような場合には、会社を分割して子会社を設立することで利益を分散するとことにより節税ができます。
資本金1億円以下の法人につきましては、所得に応じて2段階の税率を適用しています。また、法人事業税の場合についても、基本的には所得に応じて3段階の税率を適用しています。
【法人税・事業税の課税所得別税率 】
法人税の税率(資本金1億円以下の場合)
法人事業税の税率(同)
|
【具体例】
| 課税所得1,600万円の法人を分社して課税所得800万円の法人が2つとなった場合 (法人県市民税は考慮せず)
| |||||||||||||||
| 2 限度額を増やして節税する |
資本金が1億円以下の会社の場合、交際費は、その支出した事業年度で800万円までの全額を費用とすることができます。そこで、資本金1億円以下の子会社を設立すると、360万円の交際費損金算入限度額が新たに生じます。つまり、親会社と子会社(別法人)で倍の交際費損金算入限度額が利用できますから、交際費の支出が多い中小企業にとっては大いに節税になります。ただし、交際費の付替え行為は脱税となりますので、支出した法人にて適正に処理することが重要です。
| 3 子会社に値下がり資産を売却する |
所有する資産の評価替えをして、その帳簿価額を減額したとしても、一定の要件を満たすものを除いては損金に算入することはできません。
そこで、このような値下がりした資産を保有している場合には、その資産を時価で子会社に売却するのがお勧めです。結果として売却損が計上され、実質的に評価損を計上したのと同じ効果が見込まれます。
ただし、関係会社への資産の売却については、時価による譲渡が原則となっておりますので、売却損を目的として低い(高い)価格で売却することは避けるべきと思われます。
| 4 役員・従業員を転籍させて退職金を支給する |
親会社の従業員が子会社に転籍する場合には、通常、転籍前の親会社を退職し、転籍後の子会社に新たに採用されるという形態をとります。親会社から子会社への転籍とはいえ、別の法人格を持つ会社へ移ることになりますので、転籍した従業員に親会社が退職金を支払えば、その退職金の額は損金に算入されます。
同じように役員も、親会社の役員を退任し、子会社の役員に就任して、親会社が退職金を支払えば損金に算入されることになります。
ただし、形式上転籍をしても、行っている業務が従来と何も変わらない場合等には、転籍が認められない(退職金の支給が認められない)等の指摘を受ける可能性があります。形式的な転籍ではなく、実態を伴ったものとするのが重要です。
| 5 消費税の免税期間を利用する |
消費税の納税義務は、基準期間における課税売上高の金額によって判定されます。ただし、新設法人については基準期間が無いため、期首資本金額が1000万円未満の場合には設立後2期については原則として消費税の申告義務がありません。
特に、親会社は順調に業績をのばしているが、子会社は赤字続きという場合には、「連結納税制度」を利用すると節税になります。 【具体例】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   | 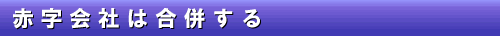 |
| 1 適格合併 |
子会社が赤字の場合、親会社はその会社の経営及び財務の両面から支援をするケースがあります。その子会社の赤字(繰越欠損金)を親会社が引継つぐことができれば親会社は、大きな節税になります。
これを実現できる方法が適格合併です。
適格合併は、税法で定める一定の要件を満たす合併です。適格合併に該当した場合は、被合併法人の資産・負債を簿価で引継ぎ、消滅会社の繰越欠損金を引継げます。
つまり、親会社は、子会社の繰越欠損金を親会社の利益と相殺し節税が可能となります。
| 2 適格合併の必要要件 |
税務上、適格合併の適用を受けるためには一定の条件を満たすことが必要です。
この要件を満たさなければ、赤字会社と合併してもその繰越欠損金(税務上:別表7の金額)を引継ぐことができません。
【適格合併の適用要件】
|
| 3 株主に対する課税の取り扱い |
合併により、被合併法人の株主に対し、合併法人の株式以外の資産が交付されない場合は、旧株(被合併保法人株式)の譲渡対価は、その合併直前の旧株の帳簿価額となります。
平成19年5月1日以降の合併からは、被合併法人の株主に対して、100%合併親会社の株式以外の資産が交付されない場合は、旧株の譲渡対価は、その合併直前の旧株の帳簿価額となります
つまり、株式以外の資産が交付されなければ、株式の譲渡として課税はされません。
   | 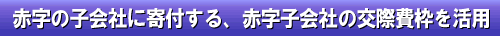 |
| 1 赤字会社に寄付をして親子会社間で利益の相殺が可能になる |
(1)赤字子会社への寄付金枠の利用
赤字の子会社があると子会社の資金確保の問題や子会社が単独で金融機関からの借り入れができないといった問題が発生します。
ときには、支援をしなければ子会社が倒産することさえあり、親会社としての信用問題にまで発展してしまいます。その場合に親会社はどうしても金銭支援でなんとかと思うはずです。
しかし、税務調査では、子会社支援をしなければならないことを理解してくれないケースがあります。これは、調査担当者との意見の相違ということになりますが、これを逆に考えると、寄付金ならOKということです。
ですから、寄付をすることを考えた方がよいと思われます。
会社が行う寄付金は、限度額までは損金算入が可能です。そこで、赤字子会社に損金算入限度額の範囲内で、寄付する方法があります。
つまり、親会社の税務上の寄付金の限度額を計算のうえ定期的に寄付を行うことで、親会社は費用にし、赤字の子会社は欠損の解消をすることができるようになると思われます。
この方法は、子会社が赤字であれば毎年使うことが可能であるというメリットがあります。
寄付金の損金算入限度額はさほど大きくはありませんが、寄付金の支出がほとんど無い会社では、検討の余地があります。赤字子会社がある場合、寄付金の損金算入限度枠を利用すれば、無理な取引をして子会社に利益を移転させる必要はありません。
子会社などが決算で赤字になることが予想された親会社は子会社に寄付をしましょう。現金でも貸付金の債務免除でもかまいません。赤字会社では寄付金は受贈益ですから寄付を受けた金額だけ損失がなくなります。一方 寄付をした会社では寄付金の損金不算入の規定があるので一定の限度額の範囲内で寄付を行なうようにします。
なお国外関連会社に対する寄付金は全額損金不算入ですので留意してください。
【寄付金の損金算入限度額(普通法人の場合)】
損金算入限度額
|
(2)損失とできる子会社への支援がある
法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとするとされており、一定の場合には寄附金とせずに損金に算入できる場合があります。
子会社などに対する支援が寄付金に該当するかどうかは国税庁の通達などを参考にして下さい。
連結納税対象法人間の寄付金は全額損金不算入ですので留意してください。
| 2 子会社を活用して接待交際費の枠を増やす |
交際費の節税の原則は、できるだけ福利厚生費や会議費等の他の勘定科目として処理できるように工夫することですが、これ以外に子会社を利用する方法が考えられます。
交際費の損金算入限度額は、1会社を単位として定められておりますのでこれを活用することが有効的です。つまり多額の交際費を使うような会社では、資本金1億円以下の子会社を設立すれば、800万円交際費の損金算入枠が増えることになります。
また、資本金1億円超の会社であれば、会社を分割して資本金1億円以下の会社を2つにすれば、交際費の限度枠を増やすことになります。
【交際費の損金算入限度額】
交際費とは冗費の節約などから法人税法では原則損金算入を認めていません。
しかし弱い立場の中小法人に限って交際費の損算入限度額を設けております。親会社が子会社を設立した場合にはそれぞれ交際費の損金算入限度額が計算されることになり節税につながります。
ただし 連結納税を行なう親子会社では親会社の限度額の範囲内でしか限度額を認めていませんので留意してください。交際費の損金算入限度額は、次のとおりです。
| 期末資本金額 | 損金算入限度額 |
| 1億円以下 | 交際費の額と800万円定額控除額のいずれか少ない金額 |
| 1億円超 | ゼロ |
   | 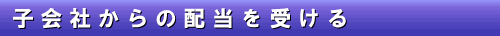 |
| 1 配当金を受け取る |
法人が内国法人から配当等を受けた場合、その配当等は会計上、収益として計上され、法人税法上は原則的に益金の額に算入されます。しかし、法人税法の別段の定めである受取配当等の益金不算入制度(法23)により、その配当等の一部または全部を益金の額に算入しないこととしています。
これは、配当を支払う法人の段階で法人税を課税し、さらに配当を受け取る法人の段階で課税する二重課税を排除する目的で設けられています。
| 2 受取配当金等の益金不算入 |
(1)連結法人株式等に係る配当等の額・・・その全額
(2)関係法人株式等に係る配当等の額
|
(3)連結法人株式等および関係法人株式等に該当しない株式等に係る配当等の額
|
(4)関係法人株式等
関係法人株式等とは、原則として次の2要件を満たす他の内国法人の発行する発行株式等をいいます。
|
| 3 配当金等の範囲 |
(1)益金不算入となる配当等の範囲
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)益金不算入とならない配当等の範囲
| ||||||||||||||||||||||||||
| 4 みなし配当 |
法人の株主等である法人が金銭等の交付を受けた場合において、交付された金銭等のの額がその法人の資本等の額のうち交付の基因となったその法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、その超過額は、益金不算入の対象となる配当等とみなします。
| ||||||||||||||||||||||
| 5 留意事項 |
受取配当等の益金不算入は、減算かつ社外流出であることから、税務調査において着目されやすい項目です。
特に負債利子の金額が大きい場合において、総資産帳簿価格の調整に誤りがあり総資産帳簿価格が過少であるときは、益金不算入額が過大となります。そのため、欠損法人においては税務リスク回避のために、実務的に確定申告書に明細書を添付せず、受取配当等の益金不算入の適用を見送る場合があります。
各種サービス
お問合せはこちら
税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください
よくあるご質問
- 相談したい時はどうしたらいいんですか?
- 結局費用はいくらかかるの?
- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。