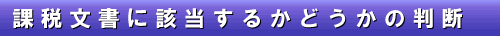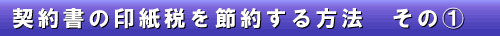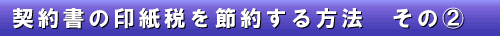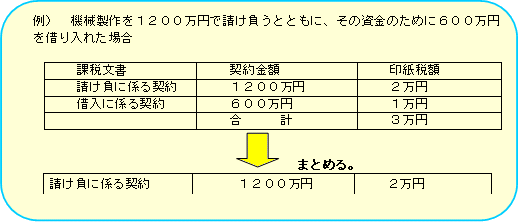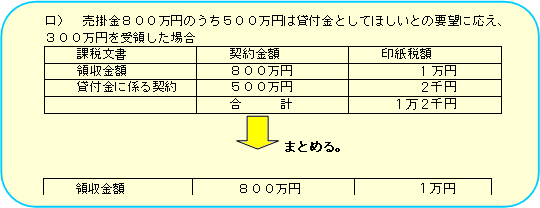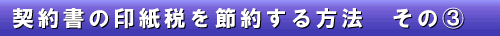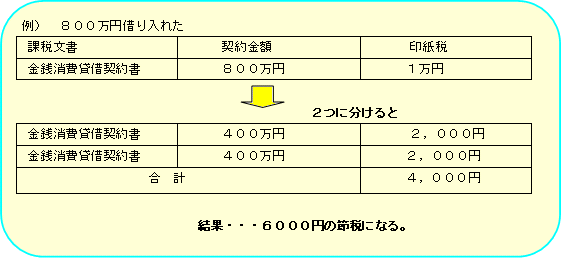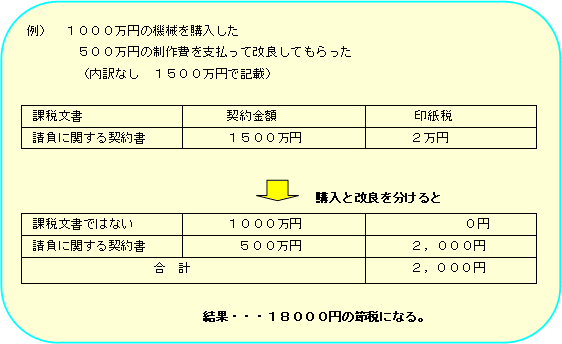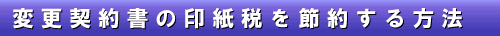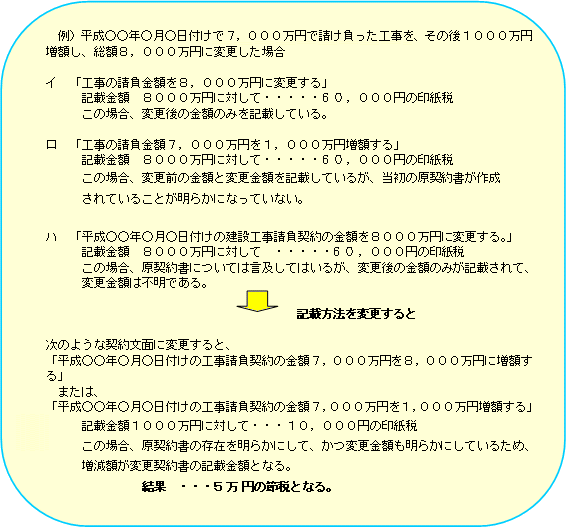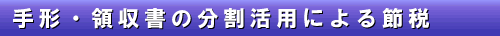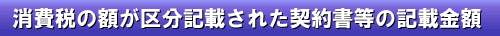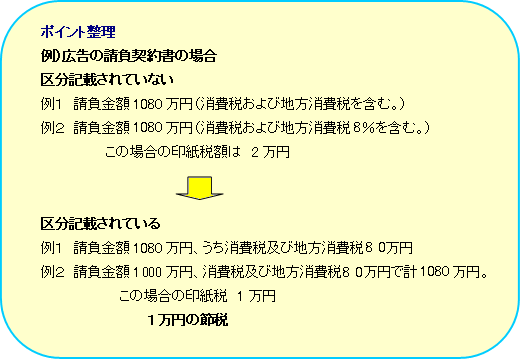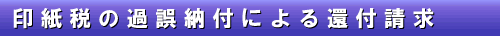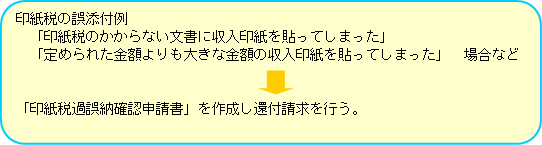契約書は、各契約当事者が1通ずつ所持するのが一般的ですが、これは「契約の当事者がそれぞれ相手方当事者等に対して成立した契約の内容を主張・証明するために作った」ということになります。
場合により、契約当事者の一方が所持するものに正本または原本と表示し、他方が所持するものに写し、副本、謄本等と表示することがあります。しかし、写し、副本、謄本等と表示された文書であっても、次のような形態のものは契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかなため、印紙税の課税対象になります。
| ① | 契約当事者の双方または一方の署名又は押印があるもの | | ② | 正本等と相違ないこと、または写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの |
|
なお、所持する文書に自分だけの印鑑を押したものは、契約の相手方当事者に対して証明の用をなさないものであるため、課税対象とはなりません。
また、契約書の正本をコピー機で複写しただけのものは、単なる写しにすぎないため課税対象とはなりません。契約書は通常、当事者間での契約の成立を目的に作成されますが、その文書が課税文書となると作成した文書の全てに印紙を貼る必要があります。1枚につき400円でも枚数が多いと金額が多くなり費用がかかります。
そこで、契約書をコピー機でコピーすることをお薦めします。
契約書の正本をコピー機で複写しただけのものは、単なる写しにすぎないため課税対象とはなりません。
つまり、契約書の控えを保存したい場合など、重要でないものはコピーで済ませることで印紙税を節約できます。
| ●5000万円の契約書 正本6部作成の場合 | 1万円×6部=6万円 | | ●正本6部のうち3部はコピーで可能な場合 | 1万円×3部=3万円 |
結果・・・ 3万円の節税となる |
特に、不動産業者は数多くの契約書を作成しますので、コピーすることで節税金額も多くなります。
単なるコピーでも、そこに当事者の署名・押印があったり、正本や原本と相違ないことの証明があると契約の成立を証明する文書となり、契約書と同じ扱いとなりますので注意が必要です。
 注意すべきは、コピーはあくまでコピーであって契約書ではないということです。コピーに署名押印してしまうとこれはコピーではなく契約書ですから、印紙を貼らなければなりません。
また「副本」とか「写」と記載しても署名押印したものは契約書とみなされ、印紙が必要です。 |
会社設立の場合、会社の目的、本店の所在地、役員などを定めた定款を作成する必要があります。
定款は公証人の認証をうけなくてはなりません。通常この認証には、公証人の手数料5万円と、収入印紙4万円が必要です。
しかし、電子定款を利用すると、課税文書に該当しないため、印紙代が不要となり、4万円の節税になります。
電子定款が利用できる条件
公証人が電子定款(電子認証)に対応している「指定公証人」が都道府県内にいること
電子定款を作成でき、特定の電子署名を持っていること |
電子署名の取得及び環境整備には数万円の費用がかかるため、1回の定款認証のためだけに電子署名を取得するのは費用的に微妙ですが、電子署名を持っていて電子定款作成に対応している行政書士に依頼すると、スムーズでリーズナブルに会社を創ることが可能となります。電子商取引にかかる法規制の見直しを盛り込んだ「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律」が4月1日から施行され、電子メール等の電子媒体を利用した契約に法的有効性が認められることになったが、これをうけて税務当局は電子データのやりとりによる契約を印紙税面での不課税文書とみなす旨を確認しました。本来、印紙税 の課税対象は「文書」であり、納税義務者はその文書の作成者とされているが、書面によることがない電子データによる契約には、従来から印紙税の課税はなじまないのではないかとする意見がありました。今回、正式に不課税である旨が確認されたことで、企業の印紙税節税が一挙に進むのではないかと見られています。印紙税は、ひとつの文書ごとに、1通、1冊を単位として課税されます。
印紙の貼付が必要な課税文書の内容が2つ以上記載されていたり、混合して記載されていても1つの文書とする取扱いになっています。
たとえば、次のような場合には節税になります。
| (1) | 2つの契約書をまとめた場合 | | | 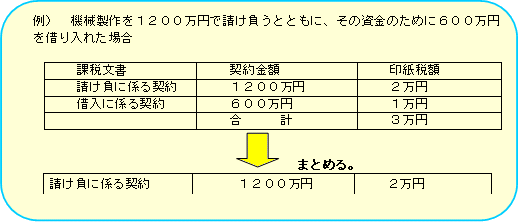 | | | ひとつの文書にまとめて契約書を作成すると、請負契約に係る文書とみなされ、2万円の印紙税で済むこととなります。結果1万円の節税となります。 | | | | (2) | 領収書と契約書をまとめた場合 | | | 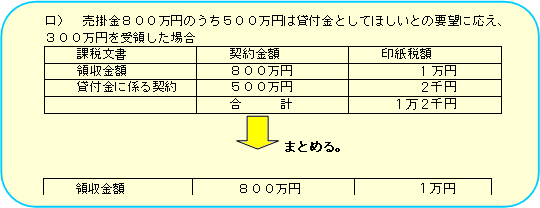 | | | ひとつの文書にまとめて契約書を作成すると、貸付金(金銭消費貸借)に係る文書となり、2,000円の印紙税で済むことになります。結果2,000円の節税となります。 |
| (1) | 請負契約書についての注意点 | | | 請負についての契約書は、印紙税額一覧表の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。
請負とは当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約をいいます。請負には建設工事のように有形的なもののほか、警備、機械保守、清掃などのように無形的な結果を目的とするものも含まれます。
具体的には、工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、会計監査契約書などが請負に関する契約書に該当します。
また、プロ野球選手や映画俳優などの専属契約書も請負に関する契約書に含まれます。
なお、請負に関する契約書に該当するものであっても、継続する複数の取引の基本的な取引条件を定めるものは、第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当することがありますのでご注意ください。 | | | | (2) | 売掛金と買掛金を相殺をする場合の注意点 | | | この場合の領収書は、相殺により売掛債権と買掛債務の消滅を証明するもので、金銭の受領を証明するものではないので収入印紙を貼る必要はありません。但し、領収書の但し書きに「上記金額の売掛金と買掛金を相殺」など、相殺したことが分かるように記載する。額面金額が相殺分だけではなく、金銭の受領も含まれる場合はその金銭の受領額に相当する収入印紙を貼る必要があります。この場合にも、相殺した金額が分かるように但し書きに記載しておきます。 | | | | (3) | 建物の賃貸借契約書の注意点 | | | 建物の賃貸借契約書には、印紙税はかかりません。ところで、建物の賃貸借契約書の中には、その建物の所在地や使用収益の範囲を確定するために、敷地の面積が記載されることがありますが、このような文書も建物の賃貸借契約書であるとして印紙税はかかりません。
しかしながら、その敷地についての賃貸借契約を結んだことが明かであるものは、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当することになります。
また、貸しビル業者などが、ビルなどの賃貸借契約又はその予約契約を締結する際などに、そのビルなどの賃借人から建設協力金又は保証金などの名目で一定の金銭を受け取り、そのビルなどの賃貸借期間に関係なく一定期間据置き後、割賦償還することなどを約する場合がありますが、このような建設協力金又は保証金などの取り決めのある建物の賃貸借契約書は印紙税額の一覧表の第1号の3文書「消費貸借に関する契約書」に該当しますのでご注意ください。 |
留意ポイント
駐車場を借りる契約の際は、その形態により印紙税の有無が分かれる。 |
土地又は地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税がかかりますが、建物や施設、物品などの賃貸借契約書は印紙税がかかりません。 したがって、駐車場の賃貸借契約書の場合は、その内容が土地の賃貸借であるのか、あるいは駐車場という施設を賃貸借するものであるのかによって、印紙税の取扱いが異なってきます。
駐車場を借りるための契約の形態には、おおむね次のようなものが考えられますが、印紙税はその形態により次のような取扱いになります。
| (1) | 駐車する場所としての土地を賃貸借する場合 | | | 駐車する場所として、いわゆる駐車場としての設備のない更地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。 | | | | (2) | 車庫を賃貸借する場合 | | | 車庫という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。 | | | | (3) | 駐車場の一定の場所に駐車することの契約の場合 | | | 駐車場という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。 | | | | (4) | 車の寄託(保管)契約の場合 | | | この契約書は、車という物品を預かる寄託契約書ですから、印紙税はかかりません。 |
2つの契約・文書を1つにまとめることで印紙税が安くなることもあれば、反対に1つの契約書を2つに分割することで印紙税が安くなる場合もあります。
例えば借入金(金銭消費貸借)に係る契約を作成する場合に、契約を分割することで節税になることがあります。
800万円の借入を行う場合、ひとつの契約書で作成すると1万円の印紙税となりますが、400万円づつに分割すると2,000円×2の4,000円の印紙税で済みます。
| (1) | 借入金の契約書を分割した場合 | | | 800万円の借入を行う場合、ひとつの契約書で作成すると1万円の印紙税となりますが、400万円づつに分割すると2,000円×2の4,000円の印紙税で済みます。 | | | 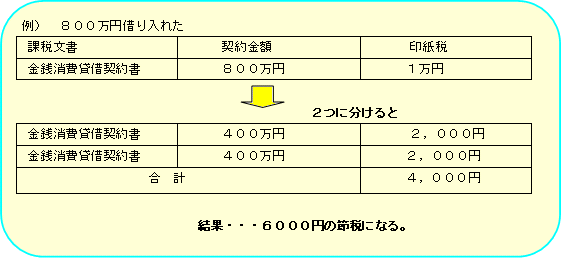 | | | | (2) | 購入の契約書、改良の契約書を分けた場合 | | | 1,000万円の機械を購入し、500万円の制作費を支払って改良してもらった場合、これを1通にまとめて「機械売買契約書」を作成し「機械代金及び改良費1,500万円」と記載してしまうと、印紙税が2万円となります。
しかし、これを「機械代金1,000万円」「改良費500万円」と文書を2つに分ければ請負に関する部分の500万円に対する印紙税2,000円だけで済むことになります。
(機械の売買契約書は課税文書ではないので、印紙税がかからないため) | | | 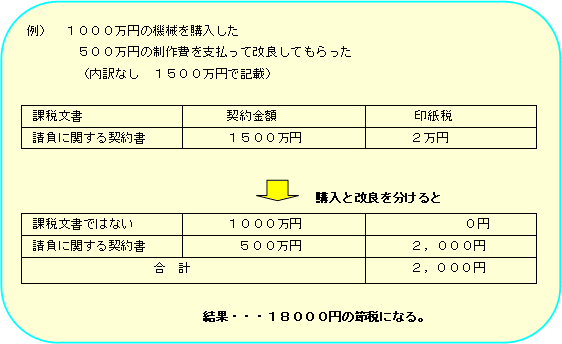 |
| (1) | 変更契約の場合の変更契約書の記載例
工事を請け負った後で、原材料や工法の変更があり価格が変動した場合などに契約金額の変更をすることがあります。変更契約書も契約書ですから、印紙税が課税されます。
しかし契約書の記載の仕方によって、印紙税額は大きく変わります。 | 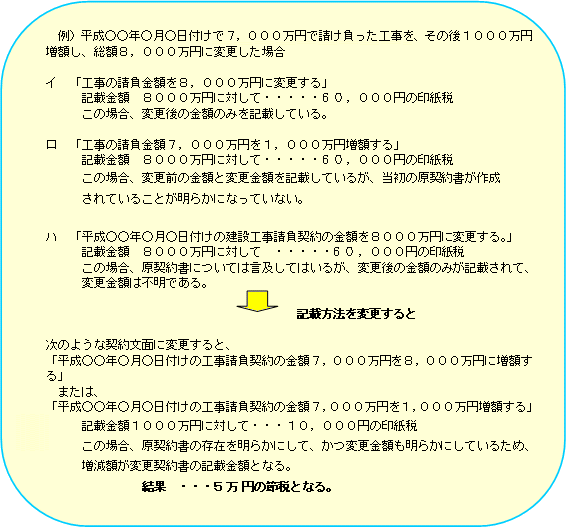 |
| 2 契約金額を変更する契約書の記載金額及び課税される記載金額の判断 | | |
留意ポイント
契約金額を変更する契約書の記載金額については、変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかであるか否かによって取り扱いが異なります。 |
(1)変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかな場合
(変更契約書に変更前の契約書の名称、文書番号または契約年月日等、変更前契約書を特定できる事項の記載があるような場合等)| ① | 変更金額が記載されている場合 | | (変更前の契約金額と変更後の契約金額が記載されていることにより変更金額を算出できる場合及び変更前の契約金額と変更後の契約金額との差額が記載されている場合も含みます。) | | | イ) | 変更金額が変更前の契約金額を増加させるものであるときは、その変更金額が記載金額。 | | | 例: | 当初の売買金額90万円を110万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円増額すると記載した文書の記載金額は、20万円。 |
| | ロ) | 変更金額が変更前の契約金額を減少させるものであるときは、その変更契約書の記載金額はないものとなります。 | | | 例: | 当初の売買金額90万円を70万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円減額すると記載した文書は、記載金額がない文書。 |
|
| | | | ② | 変更後の金額のみが記載され、変更金額が明らかでないときは、変更後の金額が記載金額となります。 | | | | 例: | 当初の売買金額を90万円に変更すると記載した文書の記載金額は、90万円。 |
|
|
|
(2)変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明かでない場合| ① | 変更後の金額が記載されているときは、変更後の金額が記載金額となります。これには、変更前の契約金額と変更金額とが記載されている等により変更後の金額を算出できる場合を含みます。 | | | 例1: | 当初の売買金額90万円を110万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円増額すると記載した文書の記載金額は、110万円。 | | 例2: | 当初の売買金額90万円を70万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円減額すると記載した文書の記載金額は、70万円。 |
| | | | ② | 変更金額のみが記載されている場合は、変更前の金額を増額するもの及び減額するもののどちらも、その変更金額が記載金額となります。 | | | | 例: | 当初の売買金額を20万円増額すると記載した文書、あるいは、当初の売買金額を20万円減額すると記載した文書の記載金額は、20万円。 |
|
|
|
|
売上金を受領するときには、領収書を発行しますし、支払いの決済手段として手形を振り出すことがありますが、これらには税法で定められた印紙を貼付する必要があります。
受取金額が大きくなると印紙税も多きくなりますが、必ずしも比例して増加するというわけではなく、段階的に増加しています。
【手形の分割活用】
例えば、10件の仕入れ先に1件あたり1,500万円を手形で支払う場合、印紙税は4,000円の10倍の4万円になります。1年間だと48万円となりますが、手形で支払いする場合の額面金額を分割すると印紙の節税ができます。1,500万円、1枚の手形を振り出した場合の印紙は4,000円になりますが、これを300万円5枚の場合、600円×5=3,000円となり1,000円の節税ができます。
10件の仕入先だと10,000円の節税になり、1年間で120,000円の節税となります。
| 1,500万円の手形 1枚 | 4,000円 | | | 300万円の手形 5枚 | 3,000円 | 節税金額・・・ 1,000円 |
|
【領収書の場合】
領収書にも手形と同じように分割することで節税ができます。
領収金額が1億1千万円の場合は、4万円の印紙が必要になりますが、これを1億円と1千万円の2枚に分割するだけで印紙は22,000円で済みます。
差引、18,000円の節税になります。年に数回あるだけで相当な節税になります。
| 領収金額 1億1千万円の1枚 | 40,000円 | | | 領収金額 1億1千万円の2枚 | 20,000円+2000円 | | | 節税金額・・・ | 18,000円 | |
|
約束手形及び為替手形は印紙税額一覧表の第3号文書に該当し、手形金額に応じて印紙税が課税されます。手形金額の記載のない手形は振出しのときは非課税ですが、その手形に後で金額を補充したときは、その補充をした人がその手形の作成者とみなされて納税義務者となります。
また、振出人の署名のない手形で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。| 【売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書】(17号文書) | | 記載された受取金額が | | 3万円未満 | 非課税 | | 3万円以上 100万円以下 | 200円 | | 100万円超 200万円以下 | 400円 | | 200万円超 300万円以下 | 600円 | | 300万円超 500万円以下 | 1千円 | | 500万円超 1千万円以下 | 2千円 | | 1千万円超 2千万円以下 | 4千円 | | 2千万円超 3千万円以下 | 6千円 | | 3千万円超 5千万円以下 | 1万円 | | 5千万円超 1億円以下 | 2万円 | | 1億円超 2億円以下 | 4万円 | | 2億円超 3億円以下 | 6万円 | | 3億円超 5億円以下 | 10万円 | | 5億円超 10億円以下 | 15万円 | | 10億円超 | 20万円 | | 受取金額の記載のないもの | 200円 | | 営業に関しないもの | 非課税 |
| | | | 【約束手形又は為替手形】(第3号文書) | | 記載された手形金額が | | 10万円未満 | 非課税 | | 10万円以上 100万円以下 | 200円 | | 100万円超 200万円以下 | 400円 | | 200万円超 300万円以下 | 600円 | | 300万円超 500万円以下 | 1千円 | | 500万円超 1千万円以下 | 2千円 | | 1千万円超 2千万円以下 | 4千円 | | 2千万円超 3千万円以下 | 6千円 | | 3千万円超 5千万円以下 | 1万円 | | 5千万円超 1億円以下 | 2万円 | | 1億円超 2億円以下 | 4万円 | | 2億円超 3億円以下 | 6万円 | | 3億円超 5億円以下 | 10万円 | | 5億円超 10億円以下 | 15万円 | | 10億円超 | 20万円 |
|
消費税の課税事業者が消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているときまたは、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合は、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。この取り扱いの適用がある課税文書は、次の3つに限られています。
①第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
②第2号文書(請負に関する契約書)
③第17号文書(金銭又は有価証券の受取書) |
| ● | 広告の請負契約書に、「請負金額1,050万円うち消費税額等50万円」と記載したとします。この場合、消費税額等50万円は記載金額に含めませんので、記載金額1,000万円の第2号文書となり、印紙税額は1万円となります。 | | | | ● | 「請負金額1,050万円 税抜価格1,000万円」と税込価格及び税抜価格の両方を具体的に記載している場合についても、消費税額等が容易に計算できることから、記載金額は1,000万円となります。 | | | | ● | 消費税額等について「うち消費税額等50万円」とではなく、「消費税額等5%を含む。」と記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えないことから、記載金額は1,050万円と取り扱われ、第2号文書の場合、印紙税額は2万円となります。 | 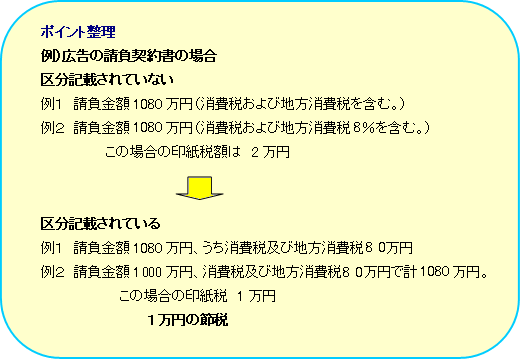 | | ● | 金銭の領収書の場合
金銭の領収書に、「商品販売代金29,000円、消費税額等1,450円、合計30,450円」と記載した場合、消費税額等の1,450円は記載金額に含めないため、記載金額29,000円の第17号の1文書となります。このとき、記載金額は3万円未満で非課税文書となり、印紙税は課税されません。 |
主な非課税文書等の具体例
※領収書(第17号文書)に関して具体的な例をあげて説明すると次のようになります。◆次の例は3万円未満となり非課税 ・領収金額 30,450円、うち消費税額 1,450円と記載
・領収金額 30,450円、税抜価格 29,000円と記載
・商品代金 29,000円、消費税額 1,450円、合計 30,450円と記載
◆次の例は3万円以上となり印紙税は200円
・領収金額 30,450円とだけ記載され、消費税に関して一切触れられていない
・領収金額 30,450円、消費税額等5%を含む、とだけ書いてある
◆次の例は100万円以下となり印紙税は200円
・領収金額 1,047,900円、うち消費税額 49,900円と記載
・領収金額 1,047,900円、税抜価格 998,000円と記載
・商品代金 998,000円、消費税額 49,900円、合計 1,047,900円と記載
◆次の例は100万円超200万円以下となり印紙税は400円
・領収金額 1,047,900円とだけ記載され、消費税に関して一切触れられていない
・領収金額 1,047,900円、消費税額等5%を含む、とだけ書いてある |
◆払いすぎた印紙税は還付してもらえる
収入印紙に消印する前であれば、はがしてもう一度使うことはできます。又、もし消印をしてしまっても、払いすぎた印紙税は、返してしてもらうことが可能です。
税務署に用意されている「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入して、印紙税を貼り間違えた文書と一緒に所轄の税務署に提出することになります。
還付金はおよそ1ケ月程度で指定した金融機関口座に振り込まれます。
なお、同じ収入印紙でも、登録免許税として、あるいは国に対する手数料として使用する場合がありますが、この場合は印紙税として納めたわけではないので還付請求はできません。
申請様式は国税庁ホームページより
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/kagono.htm| 2 収入印紙を金券ショップで購入した場合のメリット | | |
収入印紙を金券ショップで購入した場合、通常額面金額の98%前後で売られております。1万円の印紙であれば、9,800円くらいで購入することができ、額面よりは少しだけ安くなります。又、金券ショップで収入印紙を購入した場合には他にもメリットがあります。
収入印紙を「郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」以外の場所(金券ショップ等)で購入した場合には、消費税がかかっています。そのため、消費税の課税事業者で本則課税を利用している場合には、収入印紙の購入を課税仕入にすることができ、納付すべき消費税の節税にもつなげることが可能となります。
|