熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。
税理士法人新日本(熊本市)
明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応,不動産
税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方
無料相談実施中
土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください
860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00
096-288-4080
役員退職金
   |  |
平成18年度税制改正の役員給与損金不算入制度の導入により、過大な役員退職給与の損金不算入規定が改定され、併せて役員退職給与の損金経理要件が廃止されました。
| 1 平成18年度税制改正に伴う役員退職金の取扱い |
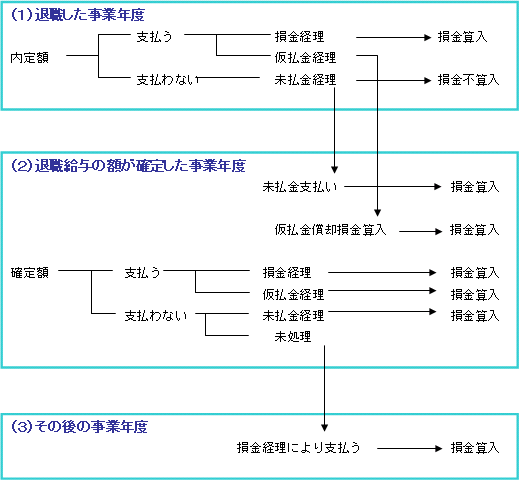 |
| 2 役員退職金過大認定回避策 |
| (1) | 役員退職金のポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 過大認定回避策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 退職金の後払い・未払い |
中小企業とって、役員退職金は、常時発生する費用ではありません。創業者やオーナー一族の退職金に当っては、高額な退職金が支給される場合が多くあります。業績の良い企業であればできるだけ早く損金算入させたいでしょうし、業績の悪い企業で、役員の退職年度が赤字決算であったり、資金繰りが苦しかったりすれば、損金算入時期を後の事業年度に持っていきたいと考えます。企業がそれぞれの立場で、役員退職金を後払いや未払いなどの支払方法で利用する場合の税務上の対策について説明します。
【未払い、後払いで注意が必要なケースと対応策】
| (1) | 事業年度の中途で役員が退職し、退職した事業年度に退職金額を未払金として損金経理した場合 | |||||
| ||||||
| (2) | 株主総会の決議が翌年以降に遅れた場合や、役員退職金を退職年度以降の年度で分割支給する場合 | |||||
| ||||||
| (3) | 法人が資金繰り等の理由で退職金の総額を未払金に計上し、その後の年度で分割支給することが行なわれた場合 | |||||
| ||||||
| ※ | いつまでに株主総会の支給決議を行えば税務上退職給与を支給したものとして取扱われるかについては、相続税法では相続財産とみなされる退職手当金について「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」(相法3条1項2号)まで該当する旨規定していますので、法人税法上も一応の目安となります。 | |||||
| 4 監査役・非常勤役員・社外取締役への支給 |
監査役や非常勤役員・社外取締役とはいえ、退職給与は税務上、原則として損金の額に算入されることになります。
しかし、過大と認められる部分の額については損金の額に算入されません。そのために、それらの役員の退職給与が過大でないと主張できる証拠等の準備をすることにより、不相当に高額である認定を受けないように対策を講じておくことが必要です。
| (1) | 税務上の留意点・対応策 | ||||||
| |||||||
各種サービス
お問合せはこちら
税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください
よくあるご質問
- 相談したい時はどうしたらいいんですか?
- 結局費用はいくらかかるの?
- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
