熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。
税理士法人新日本(熊本市)
明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応,不動産
税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方
無料相談実施中
土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください
860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00
096-288-4080
役員と会社の金銭貸借での税務調査
   | 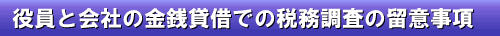 |
| 1 会社が役員に金銭を貸付けた場合 |
【利息を支払わない又は適正利率より低い利率の場合】
役員に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際に徴収した利息の額との差額に相当する金額は、役員に対して経済的利益の供与がなされたものとして課税の対象とされます。
そこで、税法では、会社と役員がお金の貸借をする場合の「適正な利率」として、次のように定めています。
| ||||||||
| (※関係法令: | 法人税法34条1項1号、法人税法34条4項、法人税基本通達9-2-9 所得税基本通達36-49) |
【利息を取らなくてよいケース】
次のような場合には、役員に対して無利息または低利による貸付けがあったとしても、適正な利息との差額が「給与」とされることはありません。
| ||||||||||
【無利息または低い利率のケース】
| ① | お金を貸した会社の税金 | ||||||
無利息または低利による貸付けとして、適正利息との差額が、役員に対する報酬または賞与として認定された場合、会社では、その認定された金額については、あくまで受け取ったものとみなし、
という処理がされることになります。 つまり、貸付金について、いったん適正な利息を受け取ったうえで、その全部または一部の金額を、役員に報酬として与えた、ということです。 そして、役員報酬とされた経済的利益は、通常の役員報酬と合算されたところで、税務上、その役員報酬が過大であるかどうか、判定されることになります。 もし、税務上、役員報酬として不相当に高額と認められる場合には、その高額とされる部分の金額は、会社の所得金額の計算上、損金に算入することはできません。 また、この場合も当然、会社には通常の報酬と同じように、源泉徴収の問題が生じることに留意してください。 | |||||||
| ② | お金を借りた役員の税金 | ||||||
| 適正な利息との差額部分が、経済的な利益として、役員報酬と認定された役員は、その金額が所得税の計算上、「給与所得」となり、通常の役員報酬と合算されたところで、所得税が計算されることになります。 | |||||||
| 2 会社が役員から金銭を借入れた場合 |
【適正利率より高い利率の場合】
適正利率を超える部分が役員報酬
お金を借りれば、当然、支払利息が発生します。これは、会社が役員からお金を借りた場合も同様です。この支払利息は、適正な利率によるものであれば、問題なく法人税の計算上、その事業年度の損金に算入されることになります。
ただし、役員に対して、通常より高い利率により利息を支払った場合には、適正な利息部分については、支払利息となりますが、それを超える部分は、法人税の計算上「役員報酬」となります。
この場合には、当然、会社側にその役員報酬に対する源泉徴収の問題が発生することになります。
さらに、適正利息を超える部分が役員報酬とされた場合には、税務上、通常の役員報酬とその支払利息の超過部分を合計したところで、その役員報酬が報酬金額として適正であるかどうか、が判定されることになります。
これらの合計金額が、役員報酬として不相当に高額であるとなった場合には、その高額であるとされた部分の金額については、その事業年度の損金に算入することができません。
【無利息または適正利率より低い利率の場合】
適正利息との差額分について、税金の問題は生じません
通常、会社がその役員からお金を借り入れるときは、会社の資金繰りが苦しい場合がほとんどだと思います。したがって、そのような借入れについては、利息を受け取っていないか、または、かなり低い利率によっていることが多いのではないでしょうか。
そうしますと、適正な利率によって利息が計算されていないことになります。
ところが、実際には、役員からの借入金については、無利息か低い利率によっているにもかかわらず、税務上の処理は何もしていない会社がほとんどです。
しかし、ほとんどの会社が、税法違反をしているかというと、そうではありません。
結論から申し上げますと、この場合には、お金を借りる側の会社においても、貸す側の役員においても、結果として、まったく税金の問題は生じないのです。
税金の問題が生じない理由
まず、話を分かりやすくするために、仮にお金を貸す側が会社であるとしましょう。
会社は、利潤の追求を目的とする営利法人ですから、どのような取引をする場合にも、常に経済合理性が要求されます。
通常、会社がその役員からお金を借り入れるときは、会社の資金繰りが苦しい場合がほとんど。税法においては、これを厳格に解釈しており、したがって、会社がその役員にお金を貸すときは、当然、適正な利率により利息を徴収すべきであり、仮に無利息または低利による貸付けを行ったときは、会社の経済合理性に反する行為として、適正利息との差額に相当する部分については、税務上は、あくまで受け取ったものとみなされ、会社の収益に計上されることになります。
一方、個人の場合は会社と違い、常に経済合理性に基づいて取引をするものではありません。
したがって、役員が会社にお金を貸し付けたとしても、当然利息を徴収すべき、ということにはならないのです。どのような条件で貸そうと、それは個人の勝手、ということです。所得税の世界では、実際に利益を受けたときに、はじめて課税が行われることになりますので、無利息の貸付けをした場合には、実際に利益を受けていないのですから、課税の問題は発生しないのです。
また、低利による貸付けを行った場合でも、その低利による利息、すなわち、受け取った利息についてのみ認識、申告すればよく、適正利息との差額が会社のように収入(所得)とみなされることはありません。(もちろん、これらの場合においては、契約書において無利息・低利としての定めがあることが前提であり、契約書上は適正利息を定めているにも関わらず、無利息や低利とした場合には、その差額が課税の対象となります。)
しかし、個人が無償による役務の提供を行った場合には所得税法第36条の規定から通常課税されないところですが、貸付の相手が同族会社であり、しかも多額の貸付金の場合には所得税の負担を不当に減少させるとして所得税法157条の規定により課税される場合が考えられますので注意が必要です。
お金を借りるということを考えれば、会社にとって借入利率は、低ければ低いほどよく、会社の経済合理性に合致することになります。
仮に適正利息によるべきとして、無利息や低利によるものは認めないとしても、税務上は、適正利息との差額部分について。
| 支払利息 ××× | / | 支払利息免除益 ××× |
| (損金算入) | (益金算入) |
という処理がされ、結果として、損金と益金が相殺されることになりますので、所得金額が発生せず、会社においても課税関係は発生しないことになります。
| (※関係法令: | 法人税法22条2項、所得税法157条、所得税基本通達36-49) |
各種サービス
お問合せはこちら
税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください
よくあるご質問
- 相談したい時はどうしたらいいんですか?
- 結局費用はいくらかかるの?
- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
