熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。
税理士法人新日本(熊本市)
明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応,不動産
税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方
無料相談実施中
土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください
860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00
096-288-4080
人事・賃金制度-職能資格制度の体系
   | 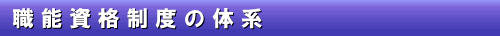 |
| 1 職能資格制度の概要 |
職能資格制度とは、社員1人1人の能力の高さを基準に、賃金や格付を決定する人事制度です。
社員の能力とは、「仕事をするために必要な能力」、つまり「職務遂行能力」を表します。
この職務遂行能力がどのぐらいのレベルにあるのかを判定し、そのレベルに応じて賃金などを決めます。それを「職能給」といいます。
職能資格は職務や役職に関係なく、従業員が保有していると思われる能力の程度に応じて"資格"が付与できることから、年功序列及びローテーションを基礎とする日本型人事制度を支えてきました。
【職務と職能】
| <職務> 「職務」は、「社員1人が担当する仕事の集まり」のことで広義に「仕事」という意味合いを持ちます。 例としては「営業職」「総務職」などです。 同じような職務でもレベルは様々で、難易度によるランク分けが重要になります。 例)「営業職1」「営業職2」 <職能> 「職能」とは、職務遂行能力を表し、仕事に求められる能力(努力次第で向上するもの)を指します。 職能は、下記の要素で成り立ちます。 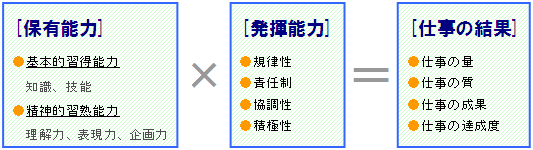 どんな仕事をするにしても、その仕事に関する知識・技能、仕事の状況に応じた判断力や企画力は必要です。そして、仕事に対する意欲も不可欠です。 職能というのは、このようにさまざまな要素を含んだ概念であり、一つの尺度で計ることは非常に困難です。 そこで、その尺度を「結果」「プロセス」「原因」の3つに分け、3方向から見るようにします。 職能資格制度は、会社が社員に期待する能力像(職能)を職種別、能力の段階別に作成し、それを基準として社員に等級を与え、昇給・人材育成といった人事制度を運用するものです。 |
【職能給制度のメリット】
|
職能給では、個人の属性によって賃金を決定するので、社員に様々な職務を経験させることができるという柔軟性に優れる反面、能力評価が適切に行われず、年齢を重ねると能力が高まるという前提の下で、年功序列的な運用につながりやすいという問題があります。
職能給をベースとした賃金体系下で、社員の高齢化にともない、職務の内容に比べて高い賃金を支払わなければならない社員が多くなったことが、日本の企業の人件費が増大する要因となっています。
| 2 初任給・昇給決定のルール |
(1)初任給の決定
基本給は、年齢給、職能給で構成されます。年齢給は18歳や22歳といった入社時の各人の年齢を年齢給表にあてはめて決定し、職能給は職能給表によって決まります。
新卒初任給としては、通常18歳を1等級に格付けし、22歳を2等級に格付けします。
職能給の額は理論的には各企業の賃金支払い方針によって決定されます。
一般的には、各企業とも従来の属人給的な給与体系から、仕事給的な給与体系へ切り換えることを目的として併存型の職能給を導入するケースが多いです。
| 職能給額 = 基本給額 - 本人給額 ( 年齢給額 + 勤続給額 ) |
一般的には、職能給と本人給との構成比が、学卒後新規採用時の初任者では3対7、標準的な40歳時従業員では5対5といった傾斜配分が行われます。
もちろん、職能給と本人給の割合をどのように決定するかは、各企業の従業員の性別、年齢構成の違いによって異なります。
具体的な例を挙げると、初任基本給が200,000円の場合、年齢給140,000円(7割)+職能給60,000円(3割)=200,000円となります。
昇給は職能給部分のウェイトを高く設定するため、年齢給と職能給のバランスは、勤続年数が増えるにつれて変化します。
40歳になった時点では、年齢給200,000円(5割)+職能給200,000円(5割)=400,000円というようになります。
(2)昇給の決定
昇給については、各等級あるいは資格に応じて初号額(基準額ともいう)が決められ、次いで同一等級内の金額範囲が決められます。同一等級内にとどまる限り、昇給はこの範囲内でしか行われません。
同一等級内の昇給は、上位等級へ移行した際に加算される昇格昇給と区分されて、習熟昇給と呼ばれます。
職能給表では、定められた初号額と、それぞれの等級ないし資格の標準的習熟昇給額、査定による昇給額区分、昇格昇給額、標準滞留年数、一定滞留年数を上回る場合の昇給の取り扱いなどを記載します。
【昇給の考え方】
| <生計費配慮の昇給> 世帯形成、年齢の上昇により生計費がアップすることに対して配慮する昇給。 これは、年齢給あるいは勤続給を毎年、あらかじめ決めた金額でアップさせていく。 <習熟昇給> 同一等級内で、職務の習熟に伴い、正確さや効率がアップしていくことに対して行われる昇給。 <昇格昇給> 担当職務や職務遂行能力の向上により、上位等級への昇格が認められた際に与えられる昇給。 |
【職能給の基本設計】
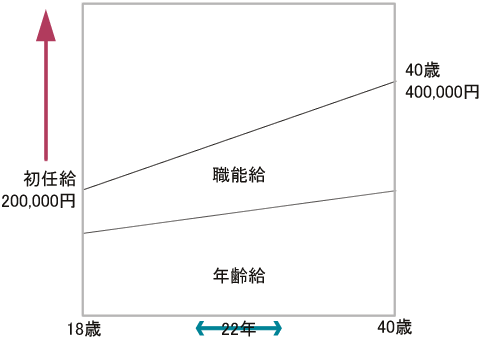
| 18歳 | 構成 | 40歳 | 構成 | |
| 年齢給 | 140,000円 | 70% | 200,000円 | 50% |
| 職能給 | 60,000円 | 30% | 200,000円 | 50% |
| 合計 | 200,000円 | 100% | 400,000円 | 100% |
(3)賃金表の内容
賃金表は「年齢給(勤続給)表」と「職能給表」の2つを使用します。
年齢給表は年齢と金額を記載した一覧表になります。
通常は、年間の標準昇給額(昇給ピッチといいいます)の3分の1程度を配分します。職能給の昇給方法には、昇格した際の昇給と同一等級内での昇給の2つがあります。いずれも人事考課の結果を反映して、昇給が行われます。
①標準滞留年数
標準的にその等級を卒業するまでの年数を設定します。
②昇格昇給
昇格昇給といい、上位等級に昇格した際に昇給させる方法があります。例えば、4等級から5等級へ昇格したとき、2,800円昇給させます。これは等級間に賃金格差を設けるための機能を有しています。
③習熟昇給
毎年、上位等級へ昇格するとは、限りません。そこで習熟昇給という昇給が行われます。これは、等級はそのままですが、その等級内の仕事や能力に深まりがみられた場合、昇給が行われる仕組みです。
通常は、等級内の号俸という形で賃金が決定されており、号俸が上がることによって昇給することになります。この昇給は、毎年昇給する定昇部分になります。
昇格昇給への配分を大きくすると、社内賃金の格差が拡がり、社員にとっては刺激的なものになります。一方、習熟昇給への配分を大きくすると、年功的な昇給になります。
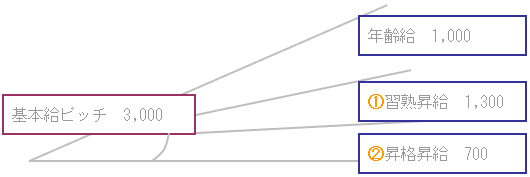
【年齢給表の例】
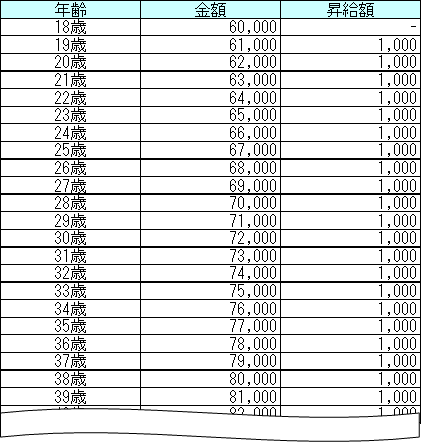
ここでは、基本給ピッチ3,000円のうち、1,000円を年齢給の昇給分に配分するということで年齢給表を作成しています。
職能給の昇給に関しては、①の1,300円が昇格に関わり無く毎年定期昇給する分です。②の700円は昇格したときに支給される昇給額です。特に②の考えは、昇格しない年は700円ずつ累積されて、昇格した年にそれまでの累積分を昇給させることになります。
【職能給表の例 10号俸昇給】
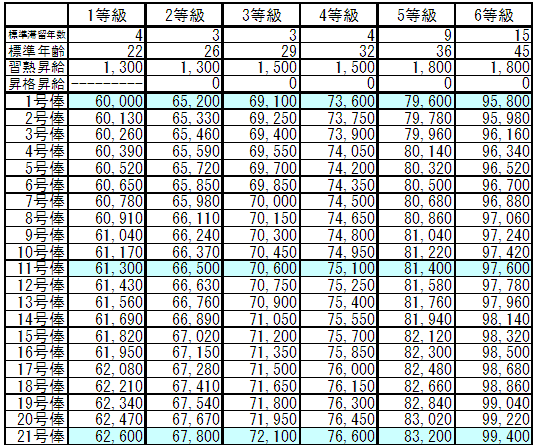
上記の職能給表(例)は、通常評価(B評価)時に10号俸昇給する例です。
評価に応じた昇給額を決定するため、習熟昇給に刻みを設定しています。
(4)職能給表の作成
職能給表を作成するためには、まず設計の型を作り、職能給傾斜の決定、昇給シミュレーションを行った上で職能給表としてまとめます。
①設計の型の作成
職能給表設計には様々なタイプがありますが、ここでは代表的なものについて紹介します。同一等級内の賃金には、号俸を用いた上で幅をもたせます。これは同一等級内でも、さまざまな能力の幅を持って、各付けされるためです。等級間の賃金には、多少の重複を認める方法を採用します。
次に、等級内の昇給カーブですが、1つの等級に留まっていれば、能力の伸びは逓減するので、上位号俸になると昇給額も減少する逓減型が理想的です。
②昇給ピッチを決める
最初に各等級毎の昇給ピッチを決めます。仮に18歳から36歳までの18年間で職能給は約99,000円昇給するものとします。
次に昇格したときの昇格昇給を決定します。これを職能給昇給額のおよそ3分の1、つまり毎年定期昇給していく習熟昇給分と昇格昇給分を2:1で分けます。
【職能給の昇給】
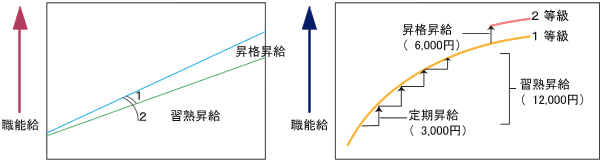
職能給傾斜を昇格昇給と習熟昇給にどのように配分するかで、基本給の性格が変わります。昇格昇給を高くすると。職能給は格差の厳しいものになり、定昇も小さくなります。一方、習熟昇給を大きくすると、職能給は刺激の少ない年功給に近いものになってしまいます。
③昇給シミュレーション
各社員の等級を決定した上で、現行賃金を新制度に移行し、数年先までの昇給シミュレーションを実施します。また、職能資格等級フレームで設定したモデル経験年数をもとに、標準昇給した場合のシミュレーションも実施し、職能給表の検討を行います。
(5)評価制度の内容
職能資格制度で用いられる評価制度は下記内容の「人事考課制度」が一般的です。
①人事考課制度
仕事の成果とそのプロセスを評価するもので、個人の持つ能力をどれだけ発揮したかを評価するものです。
また、これから発揮してくれるであろう期待能力や潜在能力も合わせて評価します。人事考課の結果は、賞与の算定、定期昇給、昇格・昇進の決定に用いられます。
②人事考課制度運用方法
イ) 考課区分
3つの要素で評価し、定量化します。
| 情意考課・・・仕事への取組姿勢、及び組織人として常識をみる 成績考課・・・仕事の結果、責任の遂行度をみる 能力考課・・・仕事の結果に影響を与えた本人の保有・発揮能力をみる |
ロ)考課段階
考課は3~5段階評定で行い、それぞれの考課要素ごとに点数を配分していきます。
| 昇格判定の5つの基準 | |
| 1 | 各等級の最短滞留年数を満たしていること |
| 2 | 考課結果が各等級の要件を満たしていること |
| 3 | レポート提出または学科試験で合格すること(等級による) |
| 4 | 上司や役員会の推薦があること(等級による) |
| 5 | 面接試験に合格すること(等級による) |
各種サービス
お問合せはこちら
税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください
よくあるご質問
- 相談したい時はどうしたらいいんですか?
- 結局費用はいくらかかるの?
- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
