熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。
税理士法人新日本(熊本市)
明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応,不動産
税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方
無料相談実施中
土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください
860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00
096-288-4080
人事・賃金制度-自社の総額人件費の適正水準を決める
   | 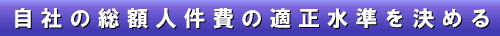 |
| 1 付加価値分析 |
賃金制度を改革するに当たって、必ずチェックしておかなければならないのは、人件費の捉え方です。どんなに立派な賃金制度を作っても、支払総額が適正な人件費率を超えてしまったのでは、何の意味もありません。
また、単純なモチベーション喚起として、人件費を底上げすることも問題です。適正人件費を超えることになれば、会社の利益が減少したり、赤字になったりします。
会社はモノを生産して販売したり、サービスを提供したりして経営活動を行っています。そして、その売上高から外部費用を差し引いた額を「付加価値」といいます。
例えば、外部から2,000万円の原材料を購入し、これを製品にして3,000万円で売ったとしたら、1,000万円が付加価値となります。
この付加価値は社員への人件費、役員報酬、株主への配当などと、会社の内外に配分され、次の経営活動にも貢献します。
このように付加価値が高いということは、様々な分配先に対して余裕のある対応ができ、何よりも人件費として支払う原資が増加します。
そして、総額人件費が、どの程度まで支払っても会社の経営に支障が出ないのか、という付加価値を基準とした人件費の管理が重要になります。
| 2 付加価値の計算法 |
| <中小企業庁方式> ①製造業及び建設業 付加価値(加工高)=生産売上高-(材料費+買入部品費+外注加工賃) ②流通販売業の場合 付加価値(粗利益)=純売上高-仕入商品原価 <日銀方式> 付加価値=純益+人件費+金融費用+賃借料+租税公課+減価償却費 |
| 3 労働分配率と労働生産性 |
(1)人件費の支払いと労働分配率
「労働分配率」とは、付加価値から支払われる人件費の割合で、次の式で表します。
| 労働分配率=人件費÷付加価値×100 |
一般的に労働分配率が低い方が会社としては有り難い訳ですが、付加価値が低く労働分配率まで低いとなると、当然に賃金は低い水準にあり社員は不満を持ちます。逆に労働分配率が高すぎると資金繰りが苦しくなります。
<事例1>
| A社 | 4,500万円÷10,000万円×100=45% |
| B社 | 4,500万円÷ 9,000万円×100=50% |
この結果、A社の方がB社よりも5%低く、他のところへの配分に余裕がある状態です。
また、両社ともに1人当たりの人件費は同じ額ですから、労働分配率が高いからといって一概に賃金が高いとも言えないことが分かります。付加価値が大きく影響しています。
(2)労働生産性
1人当たりの付加価値を「労働生産性」と言います。
付加価値÷社員数で計算する事ができます。
A社の社員は1人当たり、B社の社員より100万円余計に稼いだことが分かります。
このように労働生産性は、高いほどよく、社員数は期首と期末の平均数で割って計算します。
<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" bordercolor="#cccccc" "="" style="font-family: 'MS PGothic';">
A社 10,000万円÷10人=1,000万円 B社 9,000万円÷10人= 900万円
| 4 支払能力がどこに位置するか把握する |
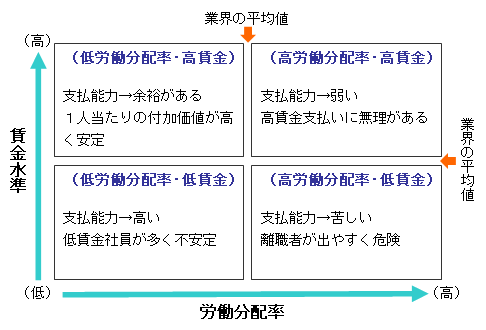
| 5 総額人件費の内訳 |
人件費は、毎月支払う給料、賞与や一時金、退職金、社会保険料などの法定福利費とその他の福利厚生費、教育訓練費など多くの内容で構成されています。
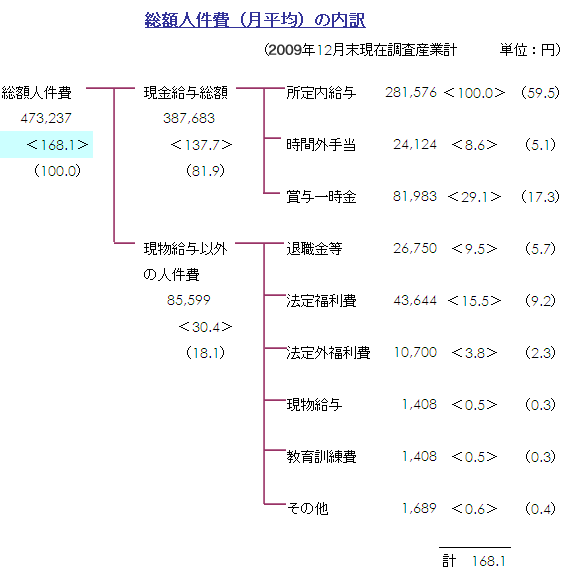
基本的な月給(毎月決まって支給される)である「所定内給与」を100としてみた場合、「総額人件費」は168.1となります。
例えば、100人の社員に平均5,000円の昇給をした場合、月額500,000円の賃金が増額となるだけでなく、840,500円が増額となり、年間にすると10,086,000円も負担が増えることになります。
このように考えると、所定内給与の管理がいかに重要かが分かります。所定内給与によって時間外手当の額も変わり、その他の人件費にも大きな影響を及ぼします。
人件費については、①所定内給与を安易に上げないこと、②退職金や賞与に連動させないことの2つのポイントが特に重要です。
なるべく所定内給与を圧縮し、利益が出たときは昇給という方法ではなく、賞与で還元した方がより安全だといえます。
| 6 適正人件費の求め方 |
(1)条件
| 年間人件費:6,600万円 付加価値率:60% 労働分配率:55% |
(2)必要売上高の算出
| 人件費÷(付加価値率×労働分配率)=必要売上高 6,600万円(人件費総額)÷{60%(付加価値率)×55%(労働分配率)}=20,000万円 |
この計算式から総額人件費を求める式に変えることができます。
(3)総額人件費の算出
| 総額人件費=売上高×付加価値率×労働分配率 |
付加価値や労働分配率の設定により総額人件費は変わりますが、付加価値を高めて賃金の原資を増やすことは重要です。
そこで総額人件費を求める場合は、付加価値率、労働分配率の目標値を設定しなければなりません。この求め方は、過去3~5年程度の数値を算出し、同業他社、同程度の規模の同業者などと比較し分析する必要があります。
| 7 適正労働分配率を決める |
適正労働分配率は、変動費率がどの程度か、それをどう削減し、どう売上増を目指すのか、目標利益をいくらに設定するのかにより変わります。
現状の労働分配率と適正労働分配率を比較して、上回っている場合は現状の人件費が業績に比べて負担になっているということです。
例えば、実際の労働分配率が60%で適正労働分配率が52%という場合、この差は8%ですから年2%ずつ4年かけて引き下げるとか、3年で適正値にするなどというように計画を立てます。
各種サービス
お問合せはこちら
税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください
よくあるご質問
- 相談したい時はどうしたらいいんですか?
- 結局費用はいくらかかるの?
- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
